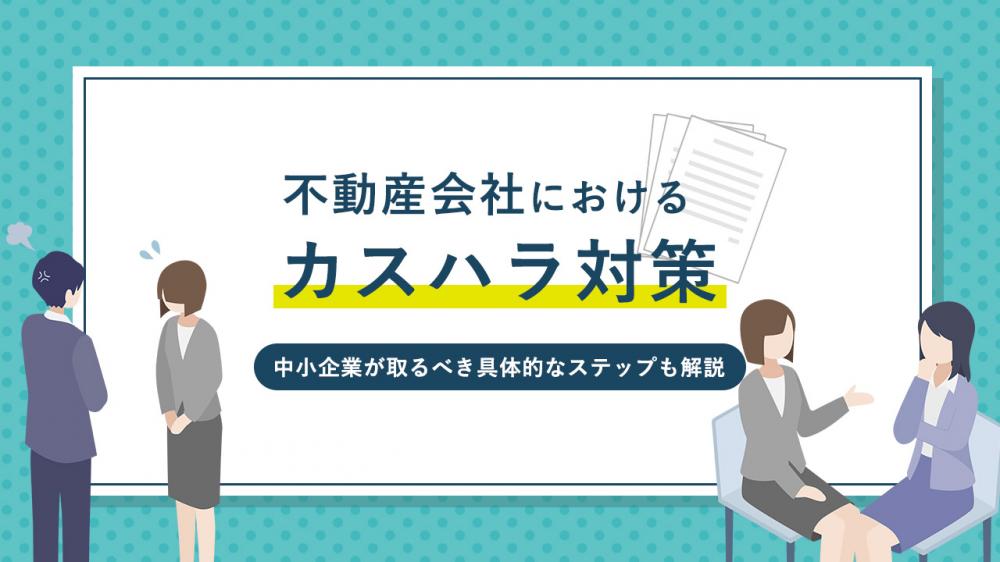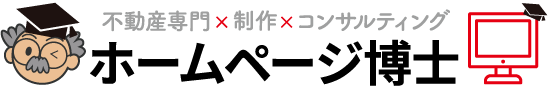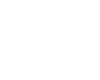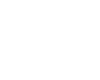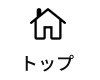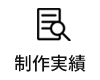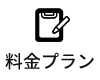近年、顧客からの過剰な要求や不当な言動、いわゆるカスタマーハラスメント(カスハラ)が社会問題として注目されています。不動産業界も例外ではありません。特に中小不動産会社においては、従業員の負担が深刻化しています。
今回の記事では、不動産業界におけるカスハラの具体例や判断基準、そして中小不動産会社が取るべき対策についてくわしく解説します。従業員の安全と企業の健全な運営を守るための参考として、ぜひご一読ください。
カスタマーハラスメント(カスハラ)とは何か?

カスタマーハラスメント(カスハラ)とは、顧客からの過度な要求や不適切な言動により、従業員の就業環境が害される行為です。不動産業界でも深刻な問題となっており、企業としての適切な対応が求められています。
この章では、カスタマーハラスメント(カスハラ)とは何かについて、次に挙げる3つの観点からくわしく見ていきましょう。
・カスタマーハラスメントの定義と特徴
・不動産業界におけるカスハラの実態
・カスハラが企業に与える影響
カスタマーハラスメントの定義と特徴
カスタマーハラスメントは、顧客からのクレームや言動のうち、要求の内容が妥当性を欠き、その手段や態様が社会通念上不相当なもので、労働者の就業環境を害するものと定義されています。
具体的には、暴言や暴力、過度なサービス要求、長時間の拘束などです。これらの行為は、従業員の精神的・身体的健康に悪影響を及ぼす可能性があります。
不動産業界では、顧客との直接的なやり取りが多く、高額な取引が絡むため、カスハラのリスクが高まりがりです。たとえば、契約内容に関する過度な要求や、物件案内時の不適切な言動などが報告されています。
これらの行為は、従業員の業務遂行に支障をきたすだけでなく、企業の信用にも影響を与える可能性があります。
カスハラの特徴は、顧客が自身の立場を利用して不当な要求を押し付ける点です。また、従業員個人への攻撃や、差別的な言動も含まれます。これらの行為は、単なるクレーム対応の範囲を超えており、企業としては明確な対応方針が必要です。
カスハラ対策とともに重要な、不動産業界の業務に欠かせない「コンプライアンス」の強化方法ついては、以下の記事で特集しています。ぜひ、そちらも参考にご覧ください。
不動産業界のコンプライアンス強化ガイド【中小企業向け実践的アプローチ】
不動産業界におけるカスハラの実態
不動産業界では、顧客からの過度な要求や威圧的な態度が問題視されています。たとえば、物件の内覧時に過剰なサービスを求められたり、契約条件の不当な変更を強要されたりするケースがあります。
これらのカスハラ行為は、従業員のストレスを増大させ、業務効率の低下を招く要因です。また、顧客からの暴言や差別的な発言も報告されており、従業員の精神的健康に深刻な影響を与えるだけでなく、職場全体の士気にも悪影響を及ぼします。
なお、中小不動産会社の新卒・中途採用の人事戦略について、以下の記事で特集しています。ぜひ、そちらも参考にご覧ください。
中小不動産会社向け人事戦略!新卒・中途採用の成功ポイントとは?
カスハラが企業に与える影響
カスハラは従業員の健康被害や、業務効率の低下を引き起こします。精神的なストレスが蓄積すると、モチベーションの低下や、最悪の場合、休職や退職に至るケースもありえるでしょう。
また、カスハラの放置は企業のブランドイメージの低下や、他の顧客へのサービス提供にも支障をきたしかねません。加えて、従業員の離職率が上昇すれば、採用や教育にかかるコストも増大します。
加えて、カスハラ問題を放置すると、雇用主が法的な責任を問われる可能性も否めません。労働契約法第5条に定められた安全配慮義務を果たしていないと判断されれば、企業は損害賠償を請求されるリスクがあります。
カスハラ対策にもつながるブランディング戦略については、以下の記事で特集しています。ぜひ、そちらも参考にご覧ください。
不動産業界で差別化を図るブランディング戦略とは?|不動産Web集客コラム
カスハラの具体例と判断基準

カスハラと正当なクレームは、大きく異なります。企業は両者の違いを理解し、常に適切な対応がとれるようにしなければなりません。
この章では、カスハラの具体例と判断基準について、次に挙げる3つの側面からくわしく見ていきましょう。
・不動産業界での具体的なカスハラ事例
・カスハラと正当なクレームの違い
・カスハラの判断基準と法的根拠
不動産業界での具体的なカスハラ事例
不動産業界では、顧客からの過度な要求や威圧的な態度が問題となる場合があります。たとえば、物件の内覧時に過剰なサービスを強要されたり、契約内容に関する不当な変更を迫られるケースも珍しくありません。
また、顧客からの暴言や差別的な発言も深刻な問題です。これらの行為は、従業員の精神的健康に悪影響を及ぼし、業務遂行に支障をきたす可能性があります。さらに、長時間にわたる拘束や執拗なクレームも、カスハラの一例です。
不動産業界におけるカスハラ対策にひと役買う「ChatGPT」の活用法について、以下の記事で特集しています。ぜひ、そちらも参考にご覧ください。
不動産業界におけるChatGPTの活用法|中小不動産会社向けガイド|不動産Web集客コラム
カスハラと正当なクレームの違い
正当なクレームは、顧客が商品やサービスに対して不満や改善点を指摘するものであり、企業の成長やサービス向上につながる建設的な意見です。
一方、カスハラは要求の内容が妥当性を欠き、手段や態様が社会通念上不相当なもので、従業員の就業環境を害する行為を指します。
具体的には、顧客が暴力的な言動を取ったり、土下座を要求するなどがカスハラに該当する行為です。これらは、正当なクレームの範囲を超えており、従業員に対する人権侵害ともいえます。
また、正当なクレームであっても、その伝え方や手段が不適切であれば、カスハラと見なされる可能性があります。たとえば、深夜に連絡を繰り返す、SNSで誹謗中傷を行うなどの行為は、手段・態様が社会通念上不相当と判断されるでしょう。
カスハラ対策としても活用できる、LINEによる顧客対応からDX推進に関しては、以下の記事でくわしく取り上げています。ぜひ、そちらも参考にご覧ください。
不動産会社を伸ばすLINE活用方法【完全ガイド】顧客対応からDX推進まで!
カスハラの判断基準と法的根拠
カスハラの判断基準として、要求内容の妥当性と、その要求を実現するための手段・態様が社会通念上相当であるかが重要なポイントです。要求内容が企業の提供する商品やサービスと無関係であったり、手段が暴力的である場合はカスハラと判断されます。
労働契約法第5条にあるように、雇用主は労働者の安全に配慮する義務(安全配慮義務)を負う立場です。つまり、企業は従業員をカスハラから保護する責任があります。適切な対応を怠ると、安全配慮義務違反として、企業が法的責任を問われかねません。
なお、2023年9月1日付けで、カスタマーハラスメントが労災の認定基準に追加されました。カスハラによる精神的・身体的被害が労災として認定される可能性が高まっています。
【不動産分野での起業を考えておられるみなさんにおすすめの記事】
不動産分野での起業の際の集客のアイデアについて、以下の記事でくわしく取り上げています。ぜひ、そちらも参考にご覧ください。
不動産起業の成功への道|アイデアから実践までの徹底ガイド|不動産Web集客コラム
中小不動産会社が取るべきカスハラ対策

不動産業界においても深刻な問題となっておりカスタマーハラスメント(カスハラ)は、特に中小不動産において従業員の大きな負担となりがちです。
この章では、中小不動産会社が取るべきカスハラ対策として、次に挙げる3項目をくわしく見ていきましょう。
・社内ポリシーの策定と従業員教育
・顧客対応マニュアルの整備と実践
・法的措置の検討と専門家への相談
社内ポリシーの策定と従業員教育
まず、カスハラに対する明確な社内ポリシーの策定が重要です。従業員はどのような行為がカスハラに該当するのかを理解し、適切な対応が可能となります。
次に、従業員への定期的な教育や研修を実施し、カスハラに対する意識の向上を図る取り組みが必要です。具体的な事例の共有や対応方法の理解によって、現場での迅速な対応が期待できます。
さらに、従業員がカスハラを受けた際に報告しやすい環境を整備するのも重要です。匿名での相談窓口を設置するなど、従業員の心理的負担を軽減する工夫が求められます。
顧客対応マニュアルの整備と実践
顧客対応に関するマニュアルを整備し、従業員が一貫した対応を取れるようにする取り組みが重要です。顧客からの不当な要求に対しても適切に対処できます。
また、マニュアルには具体的な対応手順や言葉遣いの例を盛り込み、実践的な内容とするのが望ましいです。定期的な見直しや、現場の状況に合わせた更新も必要です。
さらに、従業員同士の情報共有の促進や、顧客対応ノウハウの組織全体での共有で個々の負担を軽減できます。チームでの連携を強化し、問題解決に取り組む姿勢が必要です。
法的措置の検討と専門家への相談
カスハラが深刻な場合、法的措置の検討も必要です。弁護士などの専門家に相談し、適切な対応策を講じれていけば、企業と従業員の権利を守れます。
また、労働基準監督署や関連機関への相談も選択肢のひとつです。公的機関のサポートを受けることで、問題解決への道筋を見出せます。
さらに、社内での問題解決が難しい場合、外部の専門家によるカウンセリングやメンタルヘルスサポートを活用し、従業員の心身の健康を守ることも重要です。従業員の離職を防ぎ、職場環境の改善につなげられます。
カスハラ対策にもつながる「IT重説」活用のメリット・デメリットや、中小不動産会社が押さえるべき導入ポイントに関しては、以下の記事でくわしく取り上げています。ぜひ、そちらも参考にご覧ください。
IT重説のメリットとデメリットとは?中小不動産会社が押さえるべき導入ポイント
カスハラに対する最新の業界動向と行政の取り組み

近年、カスタマーハラスメント(カスハラ)に対する社会的関心が高まっており、不動産業界でもその対策が急務とされています。行政や業界団体は、カスハラ防止に向けた具体的な取り組みを進めています。
この章では、カスハラに対する最新の業界動向と行政の取り組みについて、次に挙げる3つの視点からくわしく見ていきましょう。
・国土交通省のカスハラ対策強化
・業界団体のガイドライン策定
・最新のカスハラ事例と判例の紹介
国土交通省のカスハラ対策強化
国土交通省は、マンション管理業務におけるカスハラ防止を目的として、管理契約のひな型である「マンション標準管理委託契約書」を5年ぶりに改定しました。
この改定では、住民から管理会社担当者へのカスハラ行為を具体的に例示し、管理組合と管理会社双方に適切な対応を求めています。
具体的なカスハラ行為として、侮辱や人格否定の発言、ネット上での誹謗中傷、執拗なつきまとい、長時間の拘束、深夜の電話などが挙げられています。これらの行為に対し、管理組合には是正に向けた配慮を、管理会社には毅然とした対応を求める内容です。
このような行政の取り組みは、業界全体でのカスハラ防止意識の向上と、具体的な対策の実施を促進するものとして期待されています。企業はこれらの動向を踏まえ、自社の対応策を見直すことが求められます。
業界団体のガイドライン策定
不動産業界の各団体も、カスハラ対策に向けたガイドラインの策定や啓発活動を進めています。これらのガイドラインは、カスハラの定義や具体例、企業としての対応策、従業員の保護措置などが詳細に示されたものです。
たとえば、公益社団法人全日本不動産協会では、不動産業におけるカスハラ対策要領を作成し、会員企業に対して周知を図っています。同要領の内容は、カスハラの具体例や対応手順、従業員教育の重要性などです。
これらのガイドラインは、企業がカスハラ対策を実施する際の指針となり、従業員の安全と業務の円滑な遂行を支援するものとして活用されています。企業はこれらを参考に、自社のポリシーやマニュアルを整備するのが望ましいでしょう。
最新のカスハラ事例と判例の紹介
近年、カスハラに関する事例や判例が増加しており、企業の対応に影響を与えています。たとえば、マンション管理業務において、住民からの過度な要求や暴言が問題となり、管理会社が法的措置を検討するケースです。
また、裁判所においても、カスハラ行為が労働者の就業環境を害するものとして、企業に対して適切な対応を求める判決が下される場合があります。これらの判例は、企業がカスハラ対策を強化する必要性を再認識させるものです。
企業は、最新の事例や判例を定期的に確認し、自社の対応策や従業員教育に反映させる責任を負っています。カスハラによるリスクを低減し、健全な労働環境を維持しなければなりません。
カスハラ対策とは別の意味で不動産会社に欠かせない、DX(デジタルトランスフォーメーション)による業務変革に関しては、以下の記事でくわしく取り上げています。ぜひ、そちらも参考にご覧ください。
不動産会社の未来を拓くDX戦略!AI・IoT・スマートホームによる業務変革
まとめ

カスタマーハラスメントは、不動産業界においても従業員の精神的負担や企業の運営に影響を及ぼす深刻な問題です。そのため、社内ポリシーの策定や従業員教育、顧客対応マニュアルの整備、そして法的措置の検討など、包括的な対策が求められます。
また、行政や業界団体の最新の取り組みやガイドラインを参考にしつつ、継続的な対応の見直しが必要です。従業員の安全を確保し、企業の信頼性と持続的な成長を実現していきましょう。